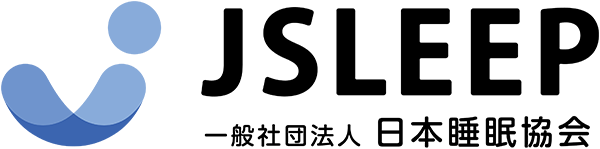さとえ学園小学校様での睡眠に関する特別授業の実施について
「睡眠から、人と社会を健やかに。」をキャッチフレーズに、睡眠に関する科学的根拠に基づいた情報の提供と具体的な施策の提案を行うことで、人々の睡眠を、より良いものにし、人と社会を健やかにしていくための活動を推進する一般社団法人日本睡眠協会(理事長:内村直尚、東京都文京区、以下「JSLEEP」)は、賛助会員である株式会社ジンズ(以下「JINS」)の睡眠をめぐる社会課題解決に向けた取り組み「寝る育(R)」の一環として、同社と共同で2024年11月19日(火)に学校法人佐藤栄学園 さとえ学園小学校(所在地:埼玉県さいたま市、校長:吉田賢司、以下「さとえ学園小学校」)4年生の児童76名に睡眠に関する特別授業を実施致しました。

- 日本人の睡眠時間は先進国のなかでも最低レベルにあるが、さらにその子どもの睡眠時間は短く、成人に向け年齢が上がるにつれてどんどん短くなる。
- 子どもの睡眠の機能として、(1)身体面では、身体の休養、疲労回復、エネルギーの保存、身体の成長(成長ホルモン分泌)、免疫機能増加、(2)脳の面では、脳の休養、疲労回復、脳の過熱を防ぐための体温下降、記憶の固定がある。
- 海外の研究では、睡眠時間が長い子ほど、早く寝ている子ほど学業の成績がよいという結果が出ている。
- 睡眠不足になると集中力が低下し、衝動性が抑制できなくなり、感情のコントロールも困難になる。
- 生体リズムは、運動、環境、社会、明暗、食事のリズムが活動と休止、自律神経、内分泌、代謝機能のリズムに作用する。
- 体内時計は光の影響を受ける。朝の光は体内時計をリセットし朝型化=早め、夜の光は夜型化=体内時計を遅らせる。
- 特にブルーライトは体内時計に強く作用するので、日中浴びた方が良く、就寝の2~3時間前は避けた方が良い。子どもは大人に比べて光に対して敏感である。
- 就寝時間が遅れて生体リズムが乱れると、知的・情緒的発達の遅れ、自律神経失調や低体温による朝の体調不良、不登校や引きこもり、意欲低下や肥満、不安・抑うつ、攻撃行動、集中力の低下、適応性の低下、落ち着きがない多動傾向、風邪をひきやすい、免疫の異常などのリスクが高まる。
- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、1-2歳児は11-14時間、3-5歳時は10-13時間、小学生は9-12時間、中学・高校生は8-10時間の睡眠時間を確保することが推奨されている。
- 睡眠によい環境づくりとしては、朝は日光を浴びて朝食をしっかり摂る、昼は適度な運動、昼寝は30分以内、嗜好品の摂りすぎに注意する、夜は寝室は適温で静かなところでブルーライトを避ける。

以上のようなお話に児童の皆様も最後まで熱心に耳を傾けて下さいました。JSLEEPとして今後も機会を捉えてこのように学校や企業での睡眠に関する普及啓発を続け、日本人の睡眠の改善に向けた取組を進めて参ります。
【協会概要】
一般社団法人日本睡眠協会
理事長 内村直尚
設立日:2023年7月20日
事務所所在地:東京都文京区本郷六丁目25番14号宗文館ビル3階
HP:https://jsleep.org/
本件に関するお問い合わせ先
日本睡眠協会事務局 contact@jsleep.org